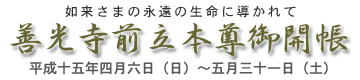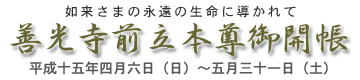| (1) |
回向柱は、「善の綱」によって「前立本尊」の中尊、阿弥陀如来の右手中指と結ばれているので、これに触れることによって、前立本尊とご縁を結ぶことができる。
|
| (2) |
回向柱の由来、インドの仏塔(stupa)への尊敬の表れに見られる。(如来の徳は天にもとどろくがごとし)
|
| (3) |
仏陀滅後、多くの弟子達によって、仏陀の教えを整理し体系化する結集がおこなわれ、その教えの偉大なことの象徴として、仏舎利・仏塔が建立される。(神聖化シンボル)
|
| (4) |
1世紀に入り、仏塔の仏殿彫刻の中に、仏陀の姿を具現しようとする傾向→ガンダーラ美術の影響→仏像へ
|
| (5) |
日本は木の文化の國と言われる。人々は木霊(こだま)と読んで、木に宿る精霊を信じ祀る習慣。
|
| (6) |
人間の生命とは比較にならないほどの長い年月、厳然と立つ樹木に生ずる素朴な宗教的感情。
|
| (7) |
先祖供養にその徳を讃えて塔姿を建てることにより、罪障消滅し悪趣を離れる功徳があると。→善光寺の回向柱=善光寺如来のお徳を象徴する、御開帳のシンボル。
|
| (8) |
回向柱は、代々松代町(藩)大回向柱寄進建立会から寄進される習わし。(現本堂は善光寺外護職であった松代藩が普請支配として建立されて以来の縁による )
現本堂は善光寺外護職であった松代藩が普請支配として建立されて以来の縁による
平成15年御開帳は、松代町西条、中村神社境内にある高さ30cm余・推定樹齢200年余の過ぎの大木が予定されている。
(前回平成9年は、同じく松代町豊栄 桑根神社社殿真後ろに聳える樹齢400年余・高さ25m・根回り3m50cmの赤松)
寸法=本堂前 1尺5寸角(約45cm)、高さ33尺(約10m)
釈迦堂前1尺角(約30cm)、高さ21尺(約6m)
|
| (9) |
大回向柱の文字
南面 奉開龕前立本尊
東面 国家豊寧 萬姓快楽 佛日増輝 含霊普潤
西面 光明遍照 十方世界 念仏衆生 摂取不捨
北面 維時 平成十五年四月吉日 一山大衆敬白
|
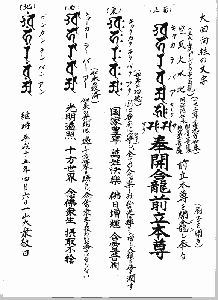 |
|
| (10) |
御開帳終了後の大回向柱
多くの参詣者の手に触れられて、如来様との結縁の大役を終えた大回向柱は、境内西に移されて土に帰るのを待つ。
現在、昭和30年御開帳の大回向柱からの8本が立っている。 |
 |
|